民泊ホストとして民泊の届け出は終わったという段階で一安心していると思いますが、実は落とし穴があります。毎年2月に「確定申告」という税金の申告時期がやってきます。民泊運営は当然ながら事業の1つであるため、あなたも事業主になり、税金の申告が必要となります。
ただいきなり税金の申告しろ!と言われてもなかなかできないと思います。事前の準備や知識が必須となるものですので、ここでどのような税金区分になり、どのような申請が必要なのかについて解説していきます。

池袋で民泊運営しながら民泊代行サービスも展開
2018年に鎌倉で民泊運営を開始。その後、民泊運営代行も運営する傍ら、池袋(東京都)でも自社の民泊を運用中。
客単価と稼働率を上げることが得意。民泊運営のリアルな情報を発信している。
1. 民泊運営はそもそも確定申告の対象になるのか?
民泊は確定申告の対象になります。
民泊新法のメリットは、届出のみで民泊の営業が可能なことです。自治体の条例で禁止されていない限り、基本的にどの地域でも合法的に民泊を提供することが可能です。その結果、届出を行う民泊として「副業」という扱いの場合と、旅館業法にて運営する「宿泊事業」の場合の2通りの分け方ができるようになりました。
いずれのタイプの民泊であっても、民泊というビジネスによって得た利益は、所得税の課税対象となります。お給料のように毎月所得税が天引きされるわけではありませんので、自分で確定申告を行って所得税の額を計算し、納税しなければなりません。
2. 民泊運営で確定申告が必要になるボーダーライン
民泊で確定申告が必要になるボーダーラインは以下のとおりです。
| 業務の扱い | 課税所得額 |
| 副業 | 20万円以上 |
| 本業 | 38万円以上 |
2-1. 副業の場合
民泊で稼いだ収入からその収入を得るためにかかった経費と一定の控除額を差し引いた後の金額(すなわち、所得金額)が20万円を超えなければ、確定申告をする必要はありません。例えば、民泊で500万円の収入を稼いだとしても、改修工事や管理費用等で合計490万円の経費がかかったとします。この場合の所得金額は10万円となりますので、確定申告をする必要はありません。しかし、民泊だけでなく、ブログ等で広告収入があり、それらと合わせると20万円を超えるといった場合は、確定申告が必要となります。
2-2. 本業の場合
民泊ビジネスを本業とする場合、所得金額が38万円を超えているのであれば、確定申告が必要です。特に旅館業を取得して運営しており、38万円以上の所得を旅館業を取得した物件からもらっている場合は例えサラリーマンとして別の収入があったとしても「本業」となります。
民泊の確定申告で必要経費はどこまで入るのか?
所得の金額を計算する上で収入から差し引くことのできる必要経費は、次の金額とされています。つまり、なんでもかんでも必要経費として計上して良いというわけではありません。経費として申告することができるものは主に下の2つのみになります。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
確定申告を行う際に使う主だった経費項目をまとめてみます。
| 勘定科目 | 内容 |
| 通信費 | 電話代、切手代、プロバイダー料金、レンタルサーバー料金 |
| 水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代のうち民泊ビジネスで利用する割合分 |
| 旅費交通費 | 民泊ビジネスを行う上で必要な交通費(電車、バス、タクシー)、ガソリン代、駐車料金、高速料金、宿泊費用 |
| 広告宣伝費 | 民泊の広告や宣伝のために要した費用 |
| 消耗品費 | 10万円未満のパソコン代、用紙代、プリンターのインク代等 |
| 事務用品費 | 筆記用具、ファイル等 |
| 修繕費 | 民泊で提供する部屋や、パソコン、事務用器具の修繕のために要した費用 |
| 新聞図書費 | 民泊を行うための教本や、情報商材等 |
| 交際費 | 民泊に係る情報交換等のために要した飲食代や懇親会の参加費用 |
| 外注費 | 民泊ビジネスを遂行するために外注を使った際の費用 |
| 減価償却費 | 10万円以上の資産(建物、パソコン、デジカメ、キャビネット等)を当該資産の耐用年数に基づいて償却した場合の当期の費用相当額 |
| 地代家賃 | 家賃、駐車場代のうち民泊ビジネスで利用する割合分 |
これらの経費項目は一例にすぎませんので、自分が行う民泊ビジネスに直接関連のある経費をしっかりと確認し、計上漏れがないように普段から管理しておく必要があります。
3. 民泊の確定申告における所得区分は3種類
確定申告は、申告する所得の種類がポイントとなってきます。というのも、所得税の計算方法は所得の種類によって異なるため、民泊ビジネスによる所得がどういった種類の所得に区分されるのかを知っておく必要があるからです。
所得税法上、所得は以下の10種類に区分されますが、民泊ビジネスに関わってくる所得は、不動産所得・事業所得・雑所得の3種類です。
それぞれ見ていきましょう。
不動産所得に該当するケース
もともと不動産業を営んでいる方が民泊事業を行った場合、不動産所得になります。
契約期間終了後に、次の入居者が決まるまで空き部屋を民泊で利用する場合がこれに当たります。
たとえば、マンスリーマンション経営をしていて空き部屋を有効活用したい場合は、この仕組みを生かして一定期間だけ民泊運営するといいでしょう。詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてみてください。
>>民泊とマンスリーを両方運営して売上を最大化する方法を知る
また、不動産所得なら赤字になっても損益通算が認められるので、節税メリットがあります。
事業所得に該当するケース
民泊を本業にしている場合は事業所得として扱います。
本業と認められるのは、事業規模が大きいかつ継続的に行われている場合です。一般的には以下の状況に当てはまることを客観的に証明する必要があります。
- 一定の規模以上のビジネスであること
- 民泊のみで生計を立てていること
- 一時的ではなく、継続的に行っている
副業だと思っていても、事業規模が大きいと事業所得とみなされるケースもあります。どうしても判断がつかない場合は、税務署に相談してみましょう。
事業所得も青色申告の承認を受けて損益通算ができます。
雑所得に該当するケース
上記2つに該当しない場合は、雑所得に該当します。雑所得とは、他の所得に当てはまらないすべての所得を指します。
自宅の一部を民泊用に提供しているような場合は、雑所得の扱いになります。この場合、自宅を購入するにあたって住宅ローン控除を適用している場合、民泊を行うとその適用が受けられない可能性があります。住宅ローン控除を適用するためには、建物(及び土地)が居住用であることが前提です。そのため、事業(民泊)として使用していると、そもそも住宅ローン控除の適用要件から外れることになってしまいますので、ご注意ください。
民泊事業は不動産所得に該当すると思っている方もいますが、民泊はただ部屋を貸しているだけでなく、寝具の提供やクリーニング、観光案内などのサービスを含むため不動産所得には該当しません。宿泊日数も限られているので、民泊は基本的に雑所得になるというのが、国税庁の公式見解です。
4.確定申告における民泊の控除額はいくら?
事業所得になるのか、雑所得になるのかは非常に重要なポイントで、この2つの所得は税金上の取り扱いが全く異なります。どのような違いがあるのか、簡単にまとめてみました。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |
| 最大65万円の青色申告特別控除(白色だと10万円) | ○ | × |
| 損失を他の所得と相殺 | ○ | × |
| 3年間の損失の繰越 | ○ | × |
| 30万円未満の少額資産の特例 | ○ | × |
| 青色事業専従者給与 | ○ | × |
事業所得で申告する場合、民泊ビジネスで生じた損失は他の所得から差し引くことができ、トータルでその年の税額を抑えることができます。引ききれなかった損失は翌年度以降に繰り越すことも可能です。事業所得に該当した方が有利だということは歴然です。しかし、事業所得とするためには、旅館業法に基づく許可申請を行う必要がありますし、税務署に対するそれ相応の理由も必要です。
5. 民泊の確定申告における税額計算の際の税率
さて、民泊ビジネスに係る所得金額が計算できたら、その所得に対してどのくらいの税金がかかってくるのか、気になりますよね。税金の額を計算する際に使用する税率は、一律ではありません。民泊ビジネスに係る所得の他、同じ分類である総合課税の所得を全て合算した金額を以下の表に照合して判断します。サラリーマンの場合、給与所得も総合課税になりますので、民泊ビジネスに係る所得に給与所得も合算した上で、判断するようにしてください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| ~195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
6.民泊の確定申告によくある質問
民泊の確定申告によくある質問をまとめると以下のとおりです。
- Airbnbで必要経費になるものは何ですか?
- 民泊は課税対象ですか?
- 民泊で車を使う場合は経費に計上できますか?
それぞれを簡潔に回答します。
Airbnbで必要経費になるものは何ですか?
先ほど紹介した経費の他にも、寝室であれば布団代や食事を提供するなら食材費などが計上されます。
民泊をスタートするにあたって不動産を獲得する際に接待交際費などが必要になった場合も計上が可能です。
Airbnbによる仲介手数料も必要経費として計上しても大丈夫です。
民泊は課税対象ですか?
民泊運営を行う以上、課税対象になります。
日本国内で収入を得る行為をし、収入を得た場合には課税対象となるため、副業であっても基準値を超えたら確定申告をする必要があります。
民泊で車を使う場合は経費に計上できますか?
明確に民泊運営で車を使う場合には経費に計上できます。
私用と社用で使い分けている場合には、民泊運営部分で使用している分のみを算出し計上しましょう。
また、民泊を行う際には本人確認が必須です。
本人確認の方法が知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。
民泊を行う際の本人確認方法を知る
7. 民泊の確定申告まとめ
民泊も一つの事業として扱われるため、初めて民泊を副業として始めたというあなたは悪戦苦闘する可能性が非常に高いです。ただ、1度経験してしまえば来年からは簡単です。
さらに、経費の落とし方もうまくすれば所得として扱わないようにして節税することもできるため、しっかりと経費の範囲などを覚えておくようにしましょう。
なお、民泊経営の平均年収やコストの抑え方が気になる方は、次の記事も参考にしてみてください。
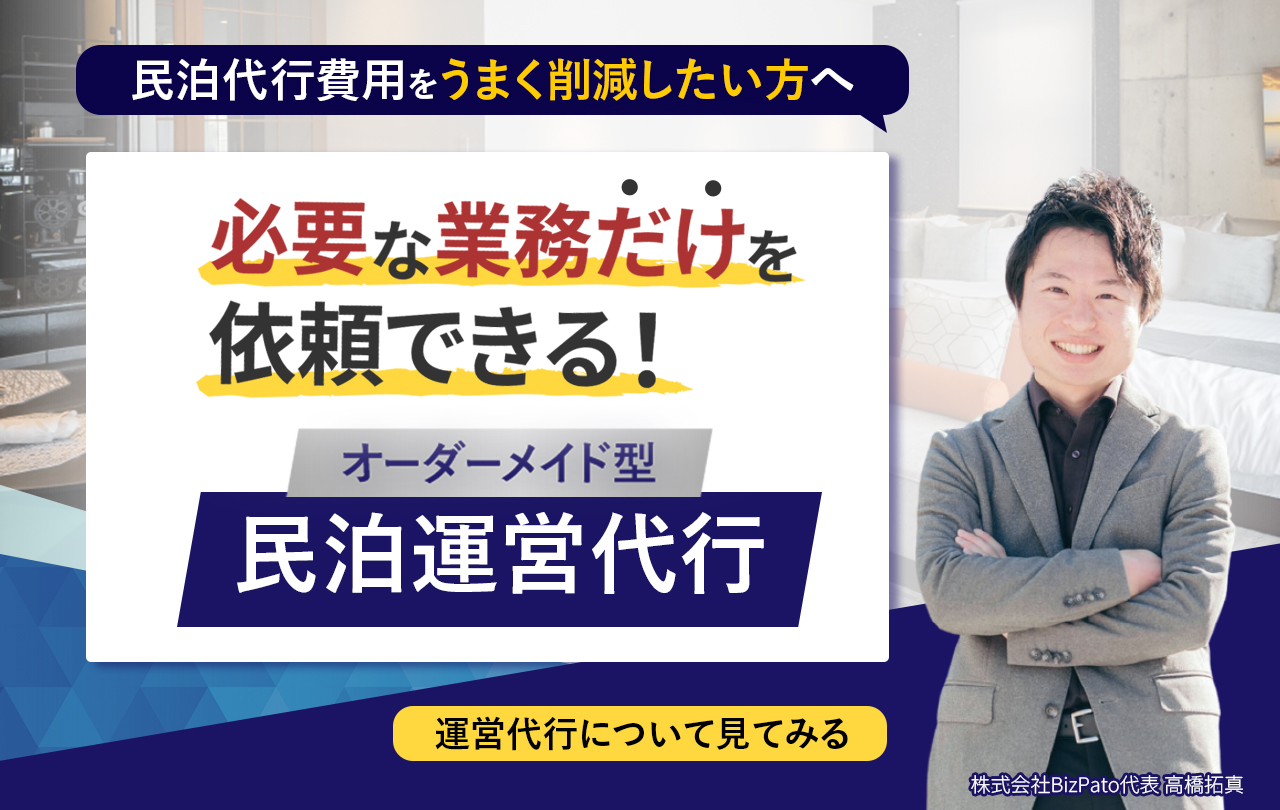
現役民泊ホストが運営代行!?
・正直、民泊関連の雑務をもうやりたくない
・民泊のプロに運営を手伝ってほしい
・代行会社に利益の大半を持っていかれるのは嫌
あなたのニーズに合わせたサービスを実現したくて、オーダーメイド型の民泊代行を始めました。
民泊が大好きな現役ホストがしっかりサポートします。
月20〜30万円の費用が発生する代行業者が多いなか、月19,800円〜の定額制なので、請求額が大きくならなくて安心。
「面倒な雑務を引き受けてくれる人がいたらいいな」と思っている方は、ぜひ弊社のサービスをチェックしてみてください。



